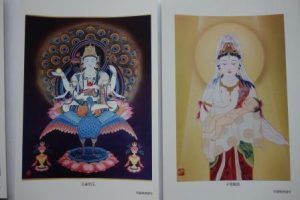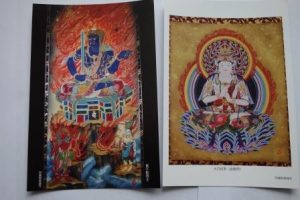2月末から3月にかけて、6泊8日のポルトガル旅行に行ってきた。ポルトガルは、ヨーロッパの中でも日本にとって、最も長い友好の歴史を持つ国の一つだ。戦国時代の1541年、ポルトガル人を乗せた中国船が種子島に漂着し、鉄砲(火縄銃)の技術を日本に伝え、その5年後にはフランシスコ・ザビエルが鹿児島に上陸しキリスト教を伝えたのが始まりだ。その頃のポルトガルは1498年ヴァスコ・ダ・ガマがインド航路を発見し、1500年にはブラジルも発見した、まさに大航海時代、ポルトガルが世界をスペインと2分する大繁栄時代だった。1582年には天正遣欧少年使節団(14~15歳の4名)が2年半かけてリスボンに到着、スペイン、イタリアなどを訪問し、1590年に帰国した。ヨーロッパに日本の存在をアピールし、彼らの持ち帰ったグーテンベルグ印刷機によって書物の活版印刷が日本で始まった。しかし、南蛮貿易で勢力を増した西国大名を警戒した江戸幕府がキリスト教禁止令や鎖国令を発し、ポルトガルとの交易が途絶えた時期もあったが、室町、安土桃山時代から江戸時代に至る密度の高い交易に寄り、ポルトガル文化が日本に浸透し、ポルトガル由来の日本語がある。ボタン、パン、タバコ、テンプラ、コンペイトウなど数多い。
羽田からフランクフルト経由でポルトガルの首都リスボンへ。乗り換え時間含めて17時間強かかり、ホテル到着は24時(現地時間)近くとなる、ヨーロッパでも最も遠い国だ。
ポルトガルの歴史は紀元前2世紀ローマ帝国の支配(その遺跡がエヴォラにある)を受け、
6世紀には西ゴート王国の支配下となり(今回は訪れなかったがリスボンのサン・ジョルジュ城は西ゴート族が築いたもの)、711年には、イスラム教徒ムーア人がアフリカからイベリア半島に侵入、722年からスペイン、ポルトガルでのレコンキスタ(イスラム教徒をイベリア半島から追い出すキリスト教徒の国土回復運動)の結果、1143年にポルトガル王国が誕生した(首都コインブラ)。以降キリスト教が支配する国となり、大航海時代を迎える。
今回ポルトガルを回ってみて、一部大航海時代前の面影も残るが、やはり大航海時代を主導したエンリケ航海王子(1394-1460)、インド航路を発見したヴァスコ・ダ・ガマ(1460~1524)、ジョアン2世の急逝の跡王位を継ぎ、全盛期を迎えた“幸運王”マヌエル1世(1469-1521)の3人が、ポルトガルの各地の建造物に足跡や名前を残している。典型的なモニュメントがリスボンのヴァスコ・ダ・ガマが出港した港に建設された“発見のモニュメント”だ。マヌエル1世の名に由来した、ゴシック様式をベースとし、海草やロープ、鎖、貝殻、天球儀などの装飾が特徴のマヌエル様式の建築物も数多くある、典型はトマールの”キリスト教修道院“で、リスボンの”ジェロニモス修道院“もそうだ。
ポルトガルのどの都市でも、建造物には特徴的な飾りが施されている。”アズレージョ“というタイルの青い飾りだ。15世紀頃ムーア人がスペイン経由でポルトガルに持ち込んだ藝術らしい。マヌエル1世がシントラの王宮に取り入れ、以降ポルトガル全土に普及し、ポルトのサン・ベント駅では2万枚のアズレージョで歴史が描かれている(1900年)。個人の家の壁にも使われている。


次の稿から順次訪問した各地を紹介する。キリスト教の三大聖地のひとつである、スペインのサンチャゴ・デ・コンポステーラも訪問した。