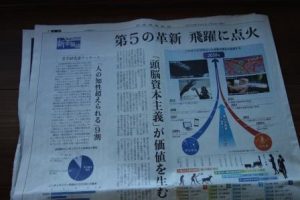あけましておめでとうございます
2019年、平成最後の新しい年が明けました。今年も東京は見事な晴天で、気持よい元旦を迎えています。昨年は地震、台風、豪雨災害など、多くの“災”に見舞われ、数多くの方々が被害にあわれました。今年こそ、今年の漢字が“幸”になるよう願いたいものです。
元日の分厚い新聞2紙に目を通す。目につくキーワードは、やはり“AI”だ。政治改革や、東京オリンピック・パラリンピックの話題に加えて、世界情勢に関する記事も多い。「2050年までにAIが人間の知性を超えられるか(シンギュラリティ)」との問いで、20~40歳代の若手研究者男女約300名に日経が調査した結果、「どちらかといえばそう思う」(33%)も含めて約9割が「そう思う」と答え、時期については2030年が18%と最も多く、2040年が16%で続いたそうだ。また、2050年に日本人の死亡原因を聞くと、自殺が最も多く(28%)、がん(24%)、老衰(9%)を上回ったという。医療技術の進歩で、まだまだ寿命が延び、自分で自分の死期を選べる時代が来ると考える人が多いのかもしれないと。生命科学やAIの飛躍的な進歩で、資本主義の常識も変わり、これからGDPは労働者の数ではなく頭脳のレベルで競い合うことになると予想する大学の先生もいる。
日経別冊(第二部)では、AIの今後の応用面を解説しながら、「AI経営してますか」と問いかけている。企業にとって2019年はAI時代に適応できる経営の具体化を問われる。すなわち、ヘルスケア分野、交通、教育、農業など幅広い分野で新たな市場や事業モデルを生み出せるか、知恵を絞る時だと指摘する。米中が、この分野でも覇権争いをする中で、日本が埋没してはならない。
昨年9月より、会社勤めから完全に離れ、完全自由な生活になった。古稀も過ぎ、1ヵ月もしないうちに72歳となる身にとっては、この年までお世話になったことに感謝している。今、世の中では高齢者にもっと働いてもらいたいとの声に押され、70歳までの雇用延長制度(企業に対する義務化)が検討されている。2017年の統計では、65歳~69歳で働く人は半分以上、70歳~74歳では30%以上と、10年前に比して就業率は増加しているそうだ。私も、何らかのお役に立てればとの気持ちはあるが、一旦気楽な生活に身を置くとますますその気持ちが薄れていく。
今年は別掲「100年時代(https://jasipa.jp/okinaka/archives/8909)」をどう生きるか、真剣に考える年としたい。まずは寿命を何歳に設定するか、今のところお陰様で元気なので85歳くらいを目標にして考えることにしたい。「息子たちに迷惑をかけず、世の中のために」を条件に。
JASIPAもどんどん活性化してきている。技術の進展が激しいときこそ、人との交流、企業間交流を活性化し、いろんな情報交換や議論を深める中で、自分自身の考えを整理することが求められのではないかと思う。JASIPAの会員が今以上に増え、より活性化することを、日本のIT企業の発展のためにも願っています。