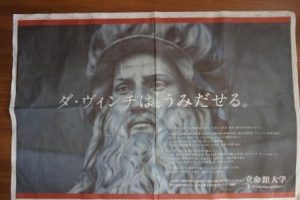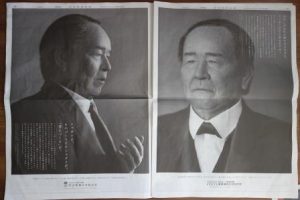3月2日の日経夕刊1面のコラムで、「アンコンシャス・バイアス」のタイトルで、法政大学総長田中優子氏が寄稿されていた。「オリンピック組織委員会前会長(森さん)の女性蔑視の発言ほど、“アンコンシャス・バイアス“の実態が見えたことはない」との主張で、紹介されており、納得性のある記事だったので紹介する。
”アンコンシャス・バイアス“に関しては、2年前当ブログで”アンコンシャス・バイアスって“と題してUPしている(https://jasipa.jp/okinaka/archives/9182)。「組織内でアンコンシャス・バイアスに意識を向けることは、職場の心理的安全性 を高め、組織と個人のパフォーマンスの向上に役立つ」との事で各企業も研修に力を入れ始めたとの紹介をした。
今回の記事によると、法政大学では2016年のダイバーシティ宣言後教職員対象に外部講師を招いて研修をしているそうだ。
”アンコンシャス・バイアス“とは、「自分では自覚できない無意識の偏見」のこと。当記事では、森氏の件に関して、下記のように言われている。
森氏は「これは解釈の仕方だ」「女性を蔑視するとかいう気持ちは毛頭ない」とおっしゃった。自覚できていないわけだから正直な気持ちだろう。JOCの山下会長は「森会長は女性役員の40%登用などかなり強力に推進していた」と述べている。私は、これは事実だと思う。その事実に対応するのが「女性理事4割、これは文科省がうるさく言うんでね」という森氏の言葉だ。つまり理解も納得もしていないが、「うるさい」ので仕方なく推進していた、と本音を述べたのだろう。
2月3日の女性蔑視の発言にも触れて、田中氏は最後に下記で締めくくっている。
本を読まず、社会の動向を学ぶこともなく、新聞も気に入る箇所しか読まない日々が想定される。年齢の問題ではない。じきに退職する私にとって、ありがたい半面教師であった。高齢者は学び続けよう。
最近、国会でも問題になっている、政治家、官僚の信じられない行動をどう考えればいいのか。「無意識の偏見」に似た「無意識の行動」ともいうべきか?なぜ普通に考えれば、変だと思うことが出来ないのか?トップへの忖度で、自由にモノが言えない、言えば降格される、そんな集団が日本を牛耳り、幹部クラスがトップに盲従している実態が恐ろしくなる。企業にはコーポレートガバナンスを強制しながら、足元がこんな状態では日本の将来が危ないと感じるのは、私だけだろうか?官僚の退職者が増え、官僚志望者が減っている現実は何を物語っているのだろうか?今のままでは日本がヤバイ!
私も、無意識の偏見、行動に陥らないように、学び続けたいと思う。